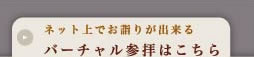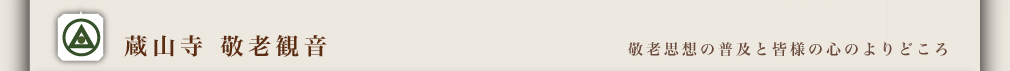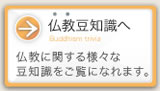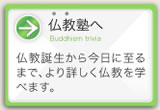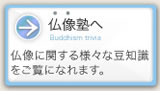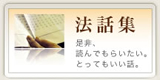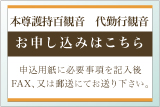2025年 2月の法話
『真俗一貫』先月は初詣ということでお正月は修正会をやって己の行いを反省し、そして本尊様に今年も宜しくお願いしますと伝え、福をもらって帰るというお話をさせてもらいました。
本日は話の流れが変わりまして、日本で一般的にお墓がどんどん建てられるようになったのはいつか見当がつきますでしょうか。私のいる群馬県をみますと大体、元禄時代を過ぎてからお墓が建つようになってきました。何故かなと考えてみたのですが、それまではやっては良いこと・やってはいけないことのルールを国が作っていたわけではなく、そこで力がある人がルールを決めていました。それがどこでも通じるわけではないですが、その中でも宗教が決めたルールだけは多くの地域で認められていました。
その中に鑑真(がんじん)さんが伝えた教えがあります。誰でも皆んな仏様になれるんだという教えも伝えました。鑑真(がんじん)さんの教えは何かというとお坊さんだけのルールを伝えたのです。しかしそれ以外にも一般の人とお坊さんと共通するルールも鑑真さんが伝えていたのですね。その共通のルールが全面に打ち出してこられたのが、比叡山をひらかれた伝教大師最澄さんなのですが、この一般の人とお坊さんの共通ルールを真俗一貫と言います。この教えは江戸時代に入って段々と認められて広まっていきました。そして元禄が終わり、ぼちぼちお葬式をするようになりました。
そのお葬式の時にこの真俗一貫の戒律をお葬式で亡くなった人にお授けするようになりました。お葬式の後に戒名を付けますが、この戒名というのが真俗一貫のお教えを受けたという証拠になります。
ところが日本の仏教界も難しいところがありまして、真俗一貫のルールには従わなくても自分たちは仏様の道を歩いていけるんだという考え方もあります。しかし、そちらの方も自分たちのルールで仏さんの道を歩いていくんだと言うのだけどお葬式はやるようになりました。こうして日本中でお葬式をやるようになりました。それに加え、江戸時代は徳川幕府がいろんなルールを徹底もしました。
皆さんから聞いているとお経を読んでも、ちっとも分からないというのが正直なところです。これは今までの仏教界の怠慢かなと思います。これから少子高齢化にもなっていきますが、仏教界は若い人たちにも分かるように伝えていかなければならないなと思います。
以上を持ちまして、2月の法要を終わりにさせていただきます。