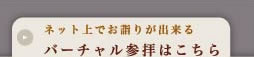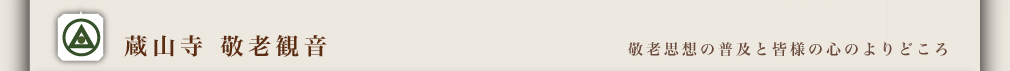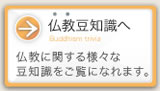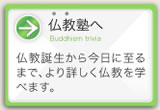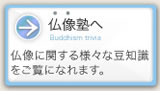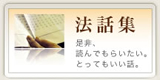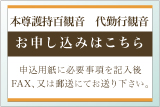2025年 10月の法話
『鑑真和上と日本に伝わった仏の戒え』ようやく秋らしくなってまいりました。前々回に鑑真(がんじん)さんのお話をしたかと思いますが、今日はその続きをお話ししたいと思います。
奈良の唐招提寺(とうしょうだいじ)には、鑑真さんがまつられております。私もこれまでに三、四回ほどお参りをいたしました。
鑑真さんという方は、唐(現在の中国)から日本へ渡ってこられる際に、実に三度も船が難破し、四度目にしてようやく日本に到着されました。その時にはすでに失明されていたといいます。
それでも「日本にどうしても正しい仏法を伝えたい」という強い願いを持って来日され、日本で正式に仏教の戒律を伝えてくださった方です。日本にとってまさに大恩人であります。
ところが、鑑真さんの晩年は決して恵まれたものではありませんでした。こういったことは教科書にはあまり書かれていません。
なぜかと申しますと、鑑真さんは中国におられた頃から「戒律」について深く考えておられたからです。
通常、戒律というのは出家した僧侶が守るべき決まりのことを指します。ですから、一般の人々が戒律を守る必要はない、というのが当時の一般的な考えでした。
戒律の根本には「僧侶は結婚してはならない」という決まりがあります。そのため、僧侶は結婚しないという形でずっと伝えられてきました。
しかし鑑真さんは、「本当に戒律は僧侶だけが受けるものなのだろうか。僧侶だけでなく、一般の人々も戒律を受けても良いのではないか」と考えるようになられたのです。
そして日本に来られてから、その考えを口にするようになりました。
すると、「とんでもないことを言うやつだ」と非難され、それ以降、表舞台に立てなくなってしまいました。
それでも、鑑真さんを慕う多くの弟子たちが集まりました。弟子たちは、「僧侶だけでなく一般の人々も戒律を受け、共に生きることができるのではないか」と考え始め、鑑真さんが唐から持ってこられた経典の中に、その考えのもととなる教えを見出しました。
その中に菩薩戒という戒律があります。これは、出家者だけでなく在家の人も受けることができる戒で、「十の重い戒め」と「四十八の軽い戒め」、あわせて五十八条からなるものです。
この戒律なら、一般の人々も受けてよいのではないかと、鑑真さんは弟子たちに伝えられました。
この「在家でも受けられる戒律」は広まり、当時の天皇であった嵯峨天皇も受戒されたと伝えられています。
嵯峨天皇は「この教えはすばらしい」とおっしゃり、とくに不殺生という戒めを非常に重んじられました。その結果、当時の日本では国家として死刑制度を廃止した時期がありました。
国として死刑を廃止するなど、世界的にも非常に珍しいことです。もっとも、その後、源平の戦乱(源氏と平氏の争い)などを経て、再び死刑は復活してしまいました。
しかし、わずかとはいえ、日本が国家として死刑を行わなかった時代があったのです。その原点には、鑑真さんの教えがあったのです。
ですから、今後「鑑真さん」という名前を耳にされたら、「一般の人にも戒律を伝えた人」あるいは「日本で死刑を100年間廃止させた教えを伝えた人」と、思い出していただければ、今は亡き鑑真さんもきっと喜ばれることでしょう。
以上を持ちまして、10月の法要を終わりにさせていただきます。